西武池袋線練馬駅から徒歩7分、桜台駅から徒歩4分
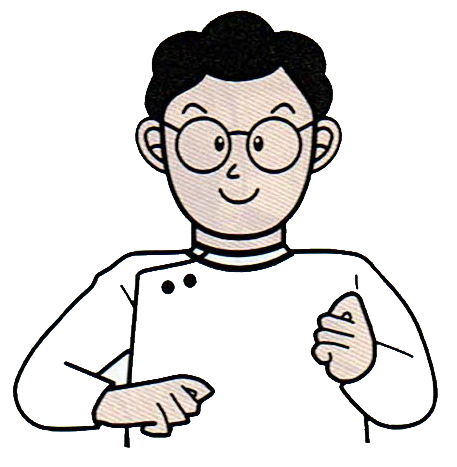
公式サイト
山下整骨院・山下鍼灸院
体性-自律神経系 生活科学研究所
Institute of Somatic Autonomic Nervous System Life Science
院長 山下和彦(博士: 生活科学/大阪市立大学)
練馬区豊玉北4ー2ー12 AM9:30~PM6:00(月~金;土・日、祝祭日は要相談)
「要予約」
鍼で高血圧が改善する理由と対象
2025年6月7日 更新
日本自律神経学会にて、2025年10月24日に「高血圧症に対する鍼通電療法の一例 第2報」と題して発表します。
高血圧を改善するためにできること
高血圧は、鍼灸治療だけでも改善が可能ですが、生活環境の悪化や基礎体力の低下によって症状が戻ることがあります。そのため、「高血圧の薬は一生飲み続けなければならない」という考えが広まっていますが、これは都市伝説のようなものです。
生活習慣の改善を継続すれば、血圧を安定させることは可能です。
高血圧のリスクと改善の可能性
高血圧は、遺伝的要素や食習慣などの生活習慣によってリスクが高まります。しかし、適切な自己管理を続けることで、健康を維持することは十分可能です。
例えば、当院では 15年間3種類の降圧剤を服用していた内科医の方 から相談を受け、鍼灸治療を行った結果、血圧が改善しました。ただし、当直勤務や寝不足の際には血圧が上昇することが確認されました。
また、独身男性で出張が多く、食事はコンビニ弁当中心、運動不足で肥満体型、仕事のストレスで睡眠不足 という方も、生活習慣の見直しと鍼灸治療を組み合わせることで、血圧が150↑/110↑から130↓/95↓まで改善しました(週1回の施術で3回目、3週目から改善傾向あり)。
まずは生活習慣の見直しから
高血圧を改善するためには、まず生活習慣を見直すことが重要です。その上で、鍼灸・手技・電気治療・運動療法 などを組み合わせることで、より効果的に血圧をコントロールできます。
特に、体重の減少に伴い血圧は必ず下がるため、適切な食事管理と運動を取り入れることが大切です。
最悪の状態では教育入院も選択肢
もし生活習慣の改善が難しく、血圧が危険なレベルにある場合は、教育入院による徹底的な生活習慣の見直しが必要になることもあります。
高血圧の基本情報を身につけ、できることから実行していきましょう。
健康な血圧を維持するために、ぜひご相談ください。
鍼灸が血圧を下げる理由
心臓や血管の働きは、自律神経 によって無意識に調整されています。鍼灸や手技療法、運動療法は 自律神経のバランスを整える 効果があり、これが血圧の安定につながることが世界中の研究で証明されています。
血圧の仕組み
血圧は、次の計算式で決まります。
血圧=心拍出量 × 末梢血管抵抗
- 心拍出量 = 1回の拍出量 × 心拍数
- 1回拍出量:心臓が1回の拍動で送り出す血液量
- 心拍数:1分間の心臓の鼓動回数
- 末梢血管抵抗:血管の硬さ
血圧をコントロールするには、心拍出量や血管の硬さに適切な刺激を加える ことが重要です。
高血圧の原因
人体の血液量は 体重の約8% を占め、体重が重いほど血液量も多くなります。
- 肥満 → 血液量が多く、心臓が大量の血液を送り出すため血圧が上昇
- 動脈硬化 → 血管が硬くなり、血流が悪くなる
- 脂質異常症 → 血液がドロドロになり、流れにくくなる
- 糖尿病 → 血液が粘り気を持ち、循環が悪化
- 腎不全 → 血液量の調節がうまくできない
- 心不全 → 心臓のポンプ機能が低下
これらの状態では、血液を全身に送るために 血圧を上げる必要がある のです。
鍼灸の降圧効果
鍼灸は、自律神経を調整し、血管の柔軟性を改善する ことで血圧を下げる効果があります。
当院では、「鍼による高血圧症への減薬効果」について研究を行い、日本自律神経学会で症例報告 をしています。
血圧を薬だけに頼らず、鍼灸・運動・生活習慣の改善 を組み合わせることで、より健康的な血圧管理が可能です。
気になる方は、ぜひご相談ください!
鍼灸が高血圧を改善する理由
高血圧は、糖尿病・腎不全・心不全 などと合併することがあり、原因不明の 本態性高血圧 も存在します。しかし、いずれも 自律神経の乱れ が関係しているため、鍼灸治療の対象となります。
血圧が上がる仕組み
血圧は 心拍出量 × 末梢血管抵抗 で決まります。
- 心拍出量:心臓が送り出す血液の量
- 末梢血管抵抗:血管の硬さ
血液量が多いほど心臓は強い圧力で血液を送り出す必要があり、肥満の人は血液量が多いため血圧が上がりやすい のです。
また、塩分を多く摂ると 体内の水分量が増え、血液量が増加 します。腎臓は余分なナトリウムを排出しようとしますが、負担が大きくなると機能が低下し、人工透析が必要になることもあります。
鍼灸が血圧を下げる理由
鍼灸は 自律神経を調整し、血管の柔軟性を改善 することで血圧を下げる効果があります。
- 交感神経の過剰な働きを抑え、心拍数を安定させる
- 血管の収縮・拡張を調整し、血流を改善する
- 腎臓の働きをサポートし、余分な塩分を排出しやすくする
実際の症例
当院では、15年間3種類の降圧剤を服用していた患者さん に週1回の鍼治療を1年間続けた結果、服薬量を半分に減らしても血圧が安定 しました。
さらに、9週間でβ遮断薬を終了 し、Ca拮抗薬・ARBの服薬量を半減 しても良好な状態を維持できています。これは、鍼刺激がCa拮抗薬やARBと同様の作用を持つ可能性 を示しています。
高血圧の改善には総合的なアプローチが重要
高血圧の治療は、薬だけに頼るのではなく、運動・食事の改善を組み合わせることが重要 です。
「美味しいものには毒がある」と言われるように、食生活の乱れや運動不足が続くと 肥満・メタボリックシンドローム につながり、血圧が上昇します。
鍼灸は 高血圧改善の選択肢の一つ ですが、運動や食事の改善と組み合わせることで、より早く効果を得ることができます。
高血圧を薬だけに頼らず、鍼灸・運動・生活習慣の改善 を組み合わせて健康を維持したい方は、ぜひご相談ください。
あなたに合った方法を取捨選択して、無理なく血圧をコントロールできる情報をご提供します!
当院に来院された高血圧の患者さんの特徴
当院には、以下のような高血圧の患者さんが来院されています。
- 本態性高血圧(原因が特定できない高血圧)
- 長期間の薬の服用(10年以上続けている方も多い)
- 薬と併用して他の治療法を試したいと考えている方
特に、10年以上薬を服用していた方 で、症状が改善した方は、以下の 生活習慣の改善 を行いながら、当院での治療を継続されました。
改善した方の共通点
- 運動不足による体重過多(体脂肪率30%以上)を改善
- 甘いもの・味の濃いもの・アルコールの摂取を控える
- 仕事や家庭での精神的ストレスを軽減する工夫をする
治療の進め方
当院では、心電図と呼吸曲線を測定 し、心臓の自律神経機能を確認します。
- 交感神経が過剰に働いているか?
- 副交感神経の働きが低下しているか?
- 自律神経のバランスが乱れていないか?
これらをチェックし、どの程度の機能低下があるか把握します。
また、患者さんの 身体の状態 に応じて治療方法を選択します。
- 身体が硬く、柔軟性がない場合 → 鍼灸・手技療法を中心に施術
- 柔軟性はあるが、筋力・筋量が低下している場合 → 運動療法を組み合わせる
患者さんの 好みや生活習慣 も考慮しながら、鍼灸・手技・運動・電気治療 を組み合わせて施術を行います。
高血圧の改善には、薬だけに頼らず、生活習慣の見直しと適切な治療を組み合わせることが重要 です。
気になる方は、ぜひご相談ください!
サイドメニュー
- 初めての方へ



