西武池袋線練馬駅から徒歩7分、桜台駅から徒歩4分
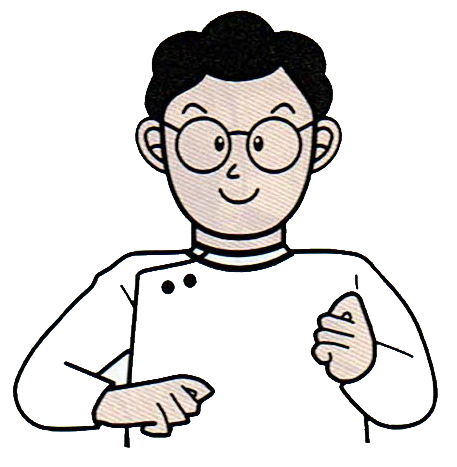
公式サイト
山下整骨院・山下鍼灸院
自律神経機能の見える化と医科学学会に基づく施術
体性-自律神経系 生活科学研究所
Institute of Somatic Autonomic Nervous System Life Science
院長 山下和彦(博士: 生活科学/大阪市立大学大学院
練馬区豊玉北4ー2ー12 AM9:30~PM6:00 03-3991-7943
(月~金;土・日、祝祭日は要相談)
慢性症状の共通点
2025年11月20日 更新日
第一の共通点
「入院するほどでもない」または「入院が嫌で自宅に帰りたい」という慢性症状の方には共通点があります。心身を自分の意思で柔軟に動かすことができないのです。落ち着いているのではなく、心身がフリーズ(凍結)して動けないのです。副交感神経機能が亢進し過ぎると心身が動けなくなるのです。お化け屋敷で本当に怖いと腰を抜かし、動けなくなり、失神するという現象が起きます。また、人が動くにはエネルギーが必要で、そのエネルギーを出すには酸素が必要ですが、肩で息をしてしまい、横隔膜を動かして腹式呼吸が出来ないのです。つまり、
1. 心身の硬さ
2. 深呼吸が出来ない・・・息が大きく吐けない
第二の共通点
無意識に心身を調整する自律神経が自動的に、環境に合わせて、適切に働いてくれない、普通ではいられない二つ目は?
自然界には「小川のせせらぎ」「そよ風」「波の音」など1/fと言われる「ゆらぎ」があって、心身の安定が保たれて落ち着くものです。
不規則な振動もゆらぎですから、電車や車の振動も気持ちの良い居眠りに導かれるのです。泣きている幼子も抱き上げて揺らして泣き止むのは、抱かれているという触覚(holding)からオキシトシンという幸せホルモンが発生するだけでなく、振動(carring)による「ゆらぎ」から落ち着きが生まれるのです。
時には自ら心身を安定させるために左右前後上下の「ゆらぎ」を激しくおこなう場合があります。興奮によって落ち着きを作ろうとすることもあるのです。これが交感神経機能の亢進による闘争と逃走です。
つまり、興奮している時はいつもの自分とは異なる不自然な余計なことをやってしまうのです。トップアスリートでも練習道理にすれば良いモノを勝手なことをやり始め、いつものことができなくなり、当たり前のことを当たり前に出来ずに格下に負けることもあるのです。これは、交感神経機能の過緊張です。この場合も2項目が当てはまります。
1. 心身の硬さ
2. 深呼吸が出来ない・・・息が大きく吐けない
自律神経の副交感神経の過緊張が背側迷走神経緊張であり、フリーズ(凍結)不動状態であり、交感神経の過緊張が闘争と逃走の可動状態で、腹側迷走神経緊張がいわゆる「ゾーンに入った状態」という、興奮しつつも客観的に周囲を落ち着いてみて判断できる状態です。
これがポリヴェーガル理論(新自律神経理論)という、自律神経を3分類させたパラダイムシフトで、2025年日本自律神経学会総会でシンポジウムも開かれました。
サイドメニュー
- 初めての方へ



